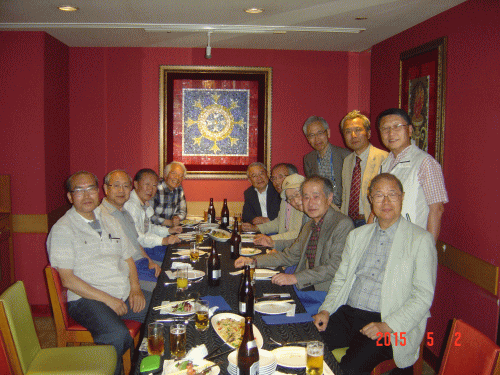
「女性に囲まれて」
1970年卒 須藤元
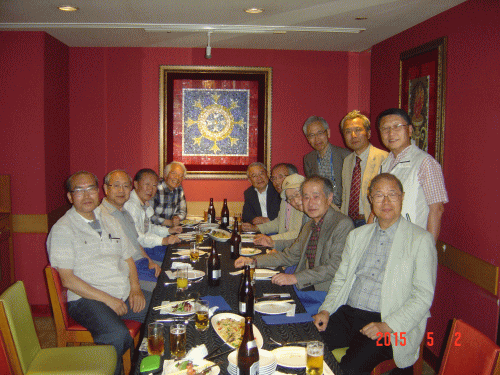
思えば、周囲に女性がたくさんいるという環境は中学以来のこと。高校は地元の高崎高校。当時、普通高校は全国どこも男子と女子が別だと思っていた。あのころのテレビの学園ドラマ「青春とはなんだ」をみて、あれ!高校にも共学があるんだと初めて知って驚いた。大学はご存じのとおり、共学といっても、500人中女性は10名である。私が女子学生と会話したのは4年間で一度だけ。10月31日に開催された母校ホームカミングデーに参加して驚いたのは学内に女性があふれていることだった。聞けば、学生の4割が女性とのこと。学内で後輩である女子学生の一人に「学長の名前は?」と聞くと、うーんと笑っていた。今の人はこんなもんかな。その2時間後のカミングデイ懇親会で私と同年の学長とちょっと話した時にこのことは話題にしなかった。
卒業後に都内新橋にある自動車専門誌の出版社に職を得た。社員は70名、女性は経理と総務に数人いるだけ。私は編集部勤務。周囲をみると机に座って勤務中でも、週刊誌や漫画を平気で読んでいる、隣の席の人と映画やレースの話題を延々と続ける、なんだかわからないが楽しそうに長電話する輩もいる。残業になって上司が帰れば、引き出しの中からウイスキー瓶を取り出す、休憩室でカードゲームをする、隣接した銭湯にいく。夜間には受付がいなくなるのでときたま勝手に社のビルに入ってくる千葉のおばちゃん(※大きな荷物を背負い、個人宅や小さなビルなどに行商して歩くバイタリティあふれる女性訪問販売業者)からピーナッツや干物を買う。外部ライターが打ち合わせや原稿をもって会社にくると、その場で干物で酒盛りか、飲み屋に直行。
社員旅行で伊豆の有名旅館に泊まれば、宴会で騒ぎ出し、襖を蹴破ったり、女湯をのぞいたり、値段のはる鯉の泳ぐ池に飛び込むなどの乱暴狼藉。後からその旅館からかなりの修理代の請求がきて心当たりあるものは上司と経理からしぼられる。バンカラ(※この言葉は今は死語)男子校の延長みたいな雰囲気だった。ふと思い出す。高校の文化祭でどっかのクラブが野犬を捕まえて解剖、すき焼きにしてしまったといううわさがあった。真実のほどは定かではない。半世紀前の話。
勤務先のような出版社には大学の文学部を出て、大手出版社をめざして、それに失敗。やむなく出版社ならどこでもいいと入る人もいた。勤務先の出版するのは自動車、オートバイの本。そのこと自体には興味がない社員もいた。編集の仕事は文芸誌だろうと趣味の本だろうと教科書だろうと原稿を仕上げて整理して印刷所に渡すという流れは共通している。ジャンルの違う出版社にいっても基本は同じ。でも、その世界に興味をもった方がいいのも確かだ。子供が好きな方が小学校教師に向いている。
私は勤務先の出している本は大学時代から読んでおり、それが入社試験を通過できた要因でもあった。よくいわれることであるが、マスコミ関係は早稲田大学出身が多いというのは事実。私の勤務先もどのセクションにも1名は同大学出の方がいた。それどころか、8名のセクションで半数は同大出身ということも体験。同じ大学出身といえ、彼らは群れることはなかった。これは1学年で4,5千人はいるマンモス大学ゆえか、同大の特性か各個人の気質かはわからない。私は大学、高校ともに後輩はなし。同族経営で別の出版社には高校後輩がいた。
社長一族は慶応大学出が多いようだ。社員でも少しいた。宴会などでその人はわーい、社長の学閥だ、いいなあ、と皆にからかわれていた。
カードゲームに関しては編集長まで参加することもあった。それには理由がある。夜間の印刷所からの校正の受け取り待ちである。それがいつになるかわからないので、常に待機体制だった。現在なら、電子メイルで片付くが、当時は印刷所の営業が現場から校正を受け取ると、タクシーや社用車で当社に持ってきて、「赤入れ」してまた市ヶ谷や小石川の印刷所の現場に戻る。最終的には「出張校正」といって、印刷所に出向いて、校正を行う。この時、校正用紙が「赤入れ」で真っ赤になってしまうこともある。そうなると、今度は印刷所の営業と現場でこんなのとてもできないよ、お願いしますの押し問答の戦いが始まる。こちらは神妙な顔してみている。あとで、現場の方へと御迷惑おかけしましたと一升瓶の差し入れが慣例。
営業と現場の葛藤といえば、出版社では編集と広告の対立がある。編集は無料で記事としてあつかうのに広告は本に載せると掲載料金をいただく。同じところ(メーカー、販売店、用品店など)に訪問する場合、編集と広告では相手側の扱いが異なる。編集側としては、いくら広告主であっても、記事としてあつかう必然性がない場合もある。私は両方のセクションを経験したので、お互いの立場はわかる。私の勤務先みたいな自動車専門誌では毎月、メーカーからの多くの広告が入るし、取材先としてメーカーとの関係は重要。取材の車、バイクはメーカーからの貸し出し車両を使う。もちろん、無料である。編集長クラスになると、取材に使うことなく、モニターとして長期使用ということで高級車を提供されることもあった。これも無料。さすがに燃料代は自分でだしたようだ。 そこで昔を思い出す。あの××変種町、いや編集長は無料提供車の日常使用ガソリン代のレシートを取材費の中にいれていたようだ。まあこれは運転自体がいつでも仕事につながるという理屈もあげられる。某H社から借りた高級スポーツカーで某役員が高速道路をドライブ。ハンドル操作を誤り、側壁に激突して1000万円の車が大破。さすが高級車、運転者は無傷だった。この事故はごく一部だけの社内秘のはずであった。でも、なぜかみんな知っている。これが会社だ。
バブル経済絶頂期の好景気のころ、メーカーはヨーロッパやアメリカでの新車発表もしばしば行った。雑誌記者などは「あごあしつき」で現地ご招待である。それでメーカー側に厳しい記事はどこまで書けるか。そのあたりは、能力ある記者は表現に工夫をこらす。現在はメーカー側からみれば雑誌媒体の価値は低下しており、前述のような無料貸与車両、海外での発表はないだろう。メーカーはテレビ、インターネット、イベントなどに宣伝戦略の重点をおき、雑誌はほっといても宣伝してくれるくらいの存在とみているようだ。
出版社というのは講談社、小学館など大手は10社くらいで、あとの多くは従業員100人以下の小規模の個人経営会社である。出版自体は資金とやる気とテーマ、そのテーマの筆者を確保できれば一人でもできる。実際に専門書の世界では一人で運営している出版社も存在している。世間的に名前が知られている割には、出版業界の規模は大きくはない。出版業界全体でも働いている人の数は2万8千人と小さな町や大企業の一つの工場の人数より少ない。これは現在、私が受給している出版厚生年金の支払い加入者の数である。
私が入社する前の昔話。我が社の2代目社長、ライバルの同規模会社の社長などと昼から麻雀。これがかけ麻雀。手持ちがなくなると経理に電話して、社員にそこまでお金を届けさせたそうだ。昼休みに食事をとりにいくよと横浜の中華街までドライブしてきた編集スタッフもいたという。実にのんびりした時代だった。私たちのころも昼飯に歩いて30分ほどの東銀座のインド料理店までいったということもあった。社長は経営者としてのセンスは確かによかったようで経済界の中心の方々とのつきあいもあったようだ。20年位前、平日の休みをとった日、夕方のラジオ番組でこの方が出演なされていたのをたまたま聞いた。ラジオであり時間帯からみて聞いている社員はいないと思ったのか「社員は金魚鉢のなかの金魚みたいなもの。適当にエサをあげていればいい」と極めて率直なことをお話ししていた。おいしいエサであったのは確かだったけど。
入社後、島根県出身で中央大学出の先輩が声をかけてくれた「おい、須藤、おれはおまえの大学に支援にいった。でも、高崎駅で警官隊に押し戻されてしまったんだ。ごめんな」 この先輩などを中心として翌年、労働組合が結成された。それにこりたのか会社側は新卒学生採用基準として、地方出身の下宿暮らしで元気で自由奔放なタイプから東京近郊在住の裕福な親元から通うおとなしいおぼっちゃんタイプに変えてしまったようだ。
1970年代当時、労働組合が強いのは小学館、平凡出版(現在のマガジンハウス)のような儲かっている会社だった。私たちも銀座にある平凡出版社の労働組合に歩いていき、組合の作り方の指導を受けた。おかげで当時は確かに給料、ボーナス(組合用語では一時金)そして売り上げで業界でも上位であった。
ともかくも1970年から80年代は社会も企業も元気で自動車、オートバイ業界は新車ラッシュ。本もいっぱい売れた。当時のスーパーカーブームの時など、小学生が会社にスーパーカーの写真くださいと押しかけてきた。
勤務先から歩いて7,8分のところはサラリーマンのメッカ、新橋飲み屋街である。新橋駅前のサラリーマンインタビューは今でもテレビでよくみるシーンである。先の先輩などは、新橋の酒場で他の出版社(※徳間書店だったと思う)の人と喧嘩さわぎ。私も酒場に入り浸り。毎日、安酒場をはしご酒。銀座も歩いていけるけど、そちらの酒場には一度もいっていない。このあたりの話は、このページではとてもおさまらないのでカット。
2000年になると、出版業界はじり貧状態。これはだれでも実感していると思う。かつてはどの町にもあった小さな本屋さんは絶滅状態。大手チェーン店も採算ベースにのらないと、2,3年で支店は閉店。つい最近も最寄り駅のツタヤが撤退。私は最終的には総務勤務であり、電話で地方書店の方からの雑誌注文を聞くこともあった。その時先方が話すのは、本が売れないという愚痴ばかり。勤務先も業務縮小で、現在、社員は40名とピーク時の半分。それでも私が携わった本は後輩達のがんばりで健在。今でも本屋さんと図書館に並んでいる。私は60歳で定年。私より10歳くらい若い後輩の人たちは定年に達しないまま50代で、やめさせられたようだ。
私の勤務先から歩いて5分ほどの別ジャンルの専門誌出版社に在籍していたのが103番に登場の2年先輩の香川さんである。香川さんとは通勤利用駅も同じの都営三田線御成門駅である。ときたま、そこで顔をあわせることもあった。退職後の最近、メイルをいただいた。お元気で活動しているようだ。香川県出身の香川さん、覚えやすい名前だ。
2年前に始めたのが「聞き書き」のボランティアだ。これはお年寄りから話を聞いてワードで小冊子にまとめて差し上げる活動。有名芸能人の個人史を得意としているプロ作家の方が地元公民館で聞き書き講座を行い、それを受講しその受講生でグループを作った。現在、14名が活動中、男は私を含めて2名、あとは女性。 指導作家の方はあちこちでその講座を行っており、それらの講座受講生を集めての交流会、飲み会というのも都内でときたま開催される。そこも女性ばかり。8月の会では40名が集まり、男は4名。女性は私の子供くらいの年齢から60代まで幅広い。聞き書きは「介護ボランティア」の一環である。このようなボランティア活動は女性が多く、同世代の男性は少ない。聞き書きの前には私は「傾聴」の講座も受講して、実際に特養老人ホームを訪問。認知症の80代お年寄りの方から「息子が来た」と抱きつかれてしまった。これは重い。ただ、話を聞くだけの傾聴はきつい。それに対して、「聞き書き」は相手の様子をみながら、お話をしていただき、それをその方の言葉でまとめていくので傾聴みたいな圧迫感はない。指導作家の方がいうには、学生時代に国語で5の成績を取った人には向いていない。文章をきれいにまとめるのではなく、その人のいう言葉そのものを文字にすること。作文能力より素直さである。
聞き書きとは別に私は15年前からパソコン(ワード、エクセル)講師を地元公民館で行っている。市の主催する初心者向けの講習である。雑誌編集という仕事を職業としたので、原稿、写真の整理、文字の種類(フォント)に字間、行間、見出しの決め方、見やすい紙面、校正という作業が「素人」よりは身についているのでワードで小冊子を作る際にも役立っている。
30年前からパソコンの魅力(魔力)にとりつかれ、これまで20台以上を使い、今も手持ちは5台。1990年前後、インターネット登場前の「パソコン通信」の時代、身辺雑記や、趣味の話などを大量に「ニフティフォーラム」にアップした。当時、それらをワープロで書き直して、冊子にして知人に配った。それは台紙にワープロ文を切り取り貼り付けてコピーしたものだ。あのころのパソコンの性能は実に低くまともなレイアウトができなかった。
それを現在、レイアウト機能のアップしたワードで整理している。まとまれば400ページ近くの個人雑誌になる。とても1冊にまとまる量ではない。ホチキスで留められない。10冊に分ける予定。
現在、聞き書きグループのHP開設を私が担当で計画中。グループリーダーのおばちゃん(私より若い)からはいつになったらできるのか、と会う度に圧力をかけられている。WINDOWS95が出たころに簡単なHPを作成したことがある。HPを作るのはそれ以来である。この文がアップされるまでに間に合えば、そのアドレスは紹介できる。
パソコンの話、それに出版業界に1980年代から導入されたDTPとそれに使用するアップル社マッキントッシュの話も長くなってしまうのでカット。ひとつだけあげる。私はマックが登場したころ、アップル2GSというマックのベースとなったパソコンを秋葉原で購入。1985年くらいだった。価格は35万円。取説はもとよりパーツ、ソフトまで、すべて英文のみである。ソフトはほとんど国内になく、アメリカの専門誌の広告をみて直接注文。悪戦苦闘の末、3年後に手放した。1989年にNECの初代98ノート購入。当時のMS-DOS3.0の時代から現在までWINDOWSである。ビル・ゲイツさんちの豪邸の庭の樹木1本くらいはMS社に払ったかな。
私はこの文を含めて、パソコン上の文章入力には「秀丸エディタ」を20年前から使用している。当時、編集者に限らず、作家、記者、学者など文章入力を主とする方々から支持されていたのがエディタである。秀丸エディタ最新バージョンは現在もネット上で入手できる。価格は4千円くらい。最終的にはワードで加工するが、秀丸エディタは思考しながら文章を作成するのに適したツールだと思う。アメリカ製ソフトの翻訳であり、もう勘弁してよといいたくなるくらいに多くの機能を詰め込んだ感のあるのがワード。秀丸はシンプルで文章作成に徹しており、安価で使いやすい。エディタは元来は、パソコンプログラムを作成するためのもので、それに日本語処理機能を加えたのだ。オートバイに喩えれば、ホンダスーパーカブとハーレーダヴィドソンみたいだ。どちらもエンジン付きの二輪車である。人間の移動手段の道具としては変わりない。あとはそれをどう使うかということだけだ。残念ながら、ハーレーはちょい乗りだけ。カブはかつての愛車であった。